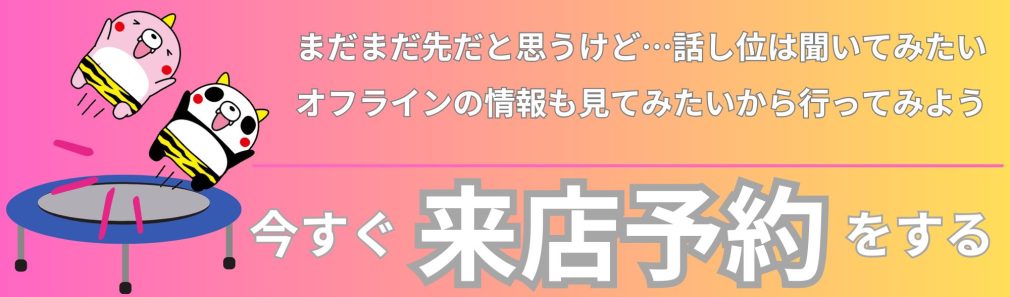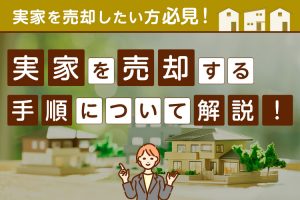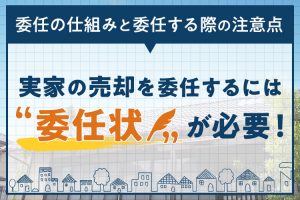マイホームの住み替えや相続をきっかけに不動産を売却する際、多くの方が気になるのが「税金」です。利益が出ると税金がかかるとは聞いていても「いくらかかるのか」「特例で減税できるのか」など、実際に進めてみないと分からないことだらけで、不安を抱える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、不動産売却時に発生する4つの主要な税金の種類や、譲渡所得の計算方法、税負担を抑えるための特例・控除制度を解説します。さらに節税につながる5つの具体的な対策も紹介していますので「できるだけ手取りを減らさずに売却したい」という方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
不動産売却でかかる4つの税金

不動産を売却すると、売却益に対する「所得税」だけでなく複数の税金が発生します。特に金額が大きくなる不動産売買では、税金の種類や支払いタイミングを正しく理解しておくことが大切です。ここでは、売却時にかかる主な4つの税金について解説します。
譲渡所得税
譲渡所得税とは、不動産の売却によって利益(譲渡所得)が出た場合にかかる税金です。つまり「買ったときより高く売れた」場合に、その利益に応じて課税されます。
譲渡所得の基本的な計算式は、以下のとおりです。
売却価格に対して、物件を購入した費用や仲介手数料など、取得や譲渡に際してかかった費用を差し引いた金額が譲渡所得です。この譲渡所得に対して、所得税(復興特別所得税含む)と住民税が課税されます。
また、マイホームや相続で取得した不動産を売却した場合でも、利益が出れば課税対象になります。ただし、3,000万円特別控除などの特例を活用すれば、大幅に税額を減らすことも可能です。
印紙税
不動産の売買契約を締結する際には「売買契約書」を作成します。この契約書に貼る収入印紙の代金として課されるのが印紙税です。税額は、契約書に記載された「契約金額」によって変動します。令和9年3月31日まで軽減措置が実施されており、税額は以下のとおりです。
|
契約金額 |
本則税率 |
軽減後の税率 |
|
500万円超1,000万円以下 |
1万円 |
5千円 |
|
1,000万円超5,000万円以下 |
2万円 |
1万円 |
|
5,000万円超1億円以下 |
6万円 |
3万円 |
実務上、印紙税の負担を抑えるために「契約書の原本は1通のみ作成し、もう一方はコピーで保管する」といった方法が取られることがあります。この場合、原本を保管する側が印紙税を全額負担するのが一般的です。事前に「どちらが原本を保管するか」や負担割合を明確にしておくと安心です。
参照元:No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁
登録免許税
登録免許税は、不動産の登記手続きにかかる税金です。不動産売却時には、主に「抵当権抹消登記」に関連して発生します。住宅ローンを利用して購入した不動産を売却する場合、売主はまずローンを完済し、登記簿上に記載されている抵当権を抹消しなければなりません。
この抵当権抹消にかかる登録免許税は、不動産1件につき1,000円です。土地が複数筆に分かれている場合は、その筆数ごとに課税される点に注意が必要です。これらの手続きは、通常は司法書士に依頼して進めます。司法書士への報酬は地域や案件の内容により異なりますが、一般的には1〜2万円程度が目安です。
また、買主名義に変更する際の「所有権移転登記」でも登録免許税が発生しますが、こちらは原則として買主が負担する費用です。ただし、契約によっては売主が一部または全額を負担するケースもあるため、契約前にしっかり確認しておくことが大切です。
消費税
不動産売却に関する消費税は「どの部分に課税されるか」を正しく理解しておくことが大切です。まず、土地は非課税とされていますが、建物部分や各種取引に付随する費用(仲介手数料・司法書士報酬など)には消費税(10%)がかかります。建物に対して消費税が課されるのは、売主が「課税事業者」の場合に限られます。主に法人や不動産会社などが該当し、個人が自宅を売却するケースでは建物にも消費税はかかりません。
また、売却時に不動産会社へ支払う仲介手数料は、消費税の課税対象です。売主・買主の双方が支払うものであり、その金額は「宅地建物取引業法」に基づいて上限が定められています。以下は、売却価格に応じた仲介手数料の上限額(税抜)をまとめた表です。
|
売却価格 |
仲介手数料の上限 |
|
400万円超 |
売却価格の3% + 6万円 + 消費税 |
|
200万円超400万円以下 |
売却価格の4% + 2万円 + 消費税 |
|
200万円以下 |
売却価格の5% + 消費税 |
例えば、売却価格が2,000万円の場合、仲介手数料の上限は「66万円(別途消費税)」となるため、消費税を加えると72万6,000円(税込)となります。費用の見積もりにおいては「税込か税抜か」を明確にしておくと、トラブルを防ぎやすくなります。
不動産売却で利益が生じた際の税金計算

不動産を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に対して税金が発生します。正確な納税額を把握するには、譲渡所得の計算方法や税率の仕組みを理解しておくことが重要です。ここでは、譲渡所得の求め方と、所有期間に応じた税率の違いについて解説します。
譲渡所得の基本計算式
不動産売却における課税対象となる「譲渡所得」は、以下の式で求められます。
取得費に含まれる主な項目は以下のとおりです。
- 購入時の本体価格
- 仲介手数料(購入時)
- 登記費用
- リフォーム費
- 不動産取得税・印紙代など
譲渡費用に含まれる主な項目は以下のとおりです。
- 仲介手数料(売却時)
- 印紙税
- 立退料
- 測量費
- 建物の解体費用など
明確な判断が難しい場合は、税理士などの専門家に確認することをおすすめします。
所有期間による税率の違い
不動産をどのくらいの期間保有していたかによって、譲渡所得にかかる税率が大きく変わります。所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」として課税され、後者のほうが税率は高く設定されています。
|
項目 |
長期譲渡所得 |
短期譲渡所得 |
|
所有期間 |
5年超 |
5年以下 |
|
税率 |
20.315% (所得税:15.315% 住民税:5%) ※所得税には2.1%の復興特別所得税を含む |
39.63% (所得税:30.63% 住民税:9%) ※所得税には2.1%の復興特別所得税を含む |
所有期間の判断基準は「売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうか」です。簡単に言えば、購入後に1月1日を6回迎えていれば「長期譲渡」、5回以下であれば「短期譲渡」として扱われます。
たとえば、令和5年1月20日に購入し令和10年1月30日に売却した場合、実際の所有期間は5年と10日あります。しかし「1月1日が5回しか通過していない」ため、短期譲渡所得として課税される点に注意が必要です。
売却時期の判断が誤ると、税率が2倍近く変わってしまうケースもあるため「所有期間の算定方法」まで正しく理解しておくことが重要です。
不動産売却で使える主な特例・控除制度

不動産を売却した際に利益(譲渡所得)が出ると、原則として税金がかかります。ただし、一定の条件を満たす場合には、税負担を軽減できる特例や控除制度がいくつか用意されています。ここでは、代表的な4つの特例について、それぞれの概要と注意点をわかりやすく解説します。
居住用財産の3,000万円特別控除
マイホームとして使用していた不動産を売却する際には「居住用財産の3,000万円特別控除」が適用できる可能性があります。この特例を使えば、売却によって生じた譲渡所得から最大3,000万円までを控除でき、課税対象となる利益を大幅に減らすことができます。例えば、譲渡所得が2,800万円だった場合、控除が適用されると課税額はゼロになります。
主な適用条件は以下のとおりです。
- 売主本人または家族が住んでいた住宅であること
- 売却時に居住している、または住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却すること
- 同一の控除を同一年内で重複して利用していないこと
相続した家でも、条件を満たせば適用可能なケースがあります。しかし、第三者に賃貸していた期間があると対象外になる場合もあるため、詳細は税理士や国税庁のHPで事前に確認しておきましょう。
参照元:国税庁|No.3302 マイホームを売ったときの特例
所有期間10年以上の軽減税率の特例
マイホームの所有期間が10年を超えている場合には「軽減税率の特例」を利用することで、譲渡所得にかかる税率をさらに抑えることが可能です。具体的には、通常20.315%(所得税15.315%※復興特別所得税含む+住民税5%)の税率が、14.21%(所得税10.21%※復興特別所得税含む+住民税4%)に軽減されます。
特に譲渡益が大きい場合は、税負担を大幅に抑えられる効果が期待できます。ただし、この軽減税率が適用されるのは課税譲渡所得6,000万円以下の部分までです。6,000万円を超える部分については、通常の税率(20.315%)が課される点に注意しましょう。
この特例は「マイホーム」として使用していた住宅が対象で、売却時に他の特例(3,000万円控除など)との併用も可能です。ただし、所有期間が10年を超えていることが前提条件となるため、登記上の取得日や譲渡日をしっかり確認することが重要です。なお、空き家であっても、かつて居住していた物件であれば対象になる可能性があるので、税理士などの専門家に確認しましょう。
参照元:国税庁|No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
居住用財産の買換え特例
自宅を売却して新たな住宅を購入(買い換え)する場合には「居住用財産の買換え特例」を利用することで、譲渡益に対する課税を一時的に繰り延べることができます。対象となるのは、売却年の前年1月1日から翌年12月31日までの期間に買い換えを行った場合で、売却益は発生していても、その年には課税されません。
ただし、この特例はあくまで「税金の免除」ではなく「将来にわたって課税を繰り延べる」制度です。つまり、買い換えた住宅を将来売却する際に、繰り延べられた譲渡益が加算され、まとめて課税される点に注意が必要です。また、売却金額が1億円以下であること、床面積が50㎡以上であることなど、複数の適用条件が設けられているため、事前に確認しましょう。
参照元:No.3355 特定のマイホームを買換えたときの特例|国税庁
相続財産の取得費加算の特例
相続で取得した不動産を売却する場合「相続財産の取得費加算の特例」を使うことで、譲渡所得を抑えることができます。この特例では、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)から3年以内に売却した場合に限り、支払った相続税の一部をその不動産の「取得費」として加算できる制度です。取得費が増えることで譲渡益が減り、その結果として課税額が軽減されます。
適用のためには、対象不動産が相続財産であること、実際に相続税を納付していること、そして売却のタイミングが「申告期限から3年以内」であることが条件です。また、加算額の算出には専門的な計算が必要となるため、申告時には税理士に相談することをおすすめします。特に不動産の評価が高く、相続税額が大きかった場合は節税効果も大きくなります。
参照元:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁
不動産売却の税金を抑えるための5つのポイント
不動産売却によって得られる利益には税金が課されますが、工夫次第で税負担を軽減することができます。ここでは、売却時のタイミングや書類の保管、経費や特例の活用など、実践しやすい節税のポイントを5つに分けて解説します。
売却時期の調整
譲渡所得税は、不動産の売却で得た利益(譲渡所得)に対して課される税金ですが、その税率は「所有期間」によって大きく異なります。5年を超えて所有していた不動産を売却した場合は「長期譲渡所得」として扱われ、税率は約20.315%に軽減されます。一方、5年以下の「短期譲渡所得」では39.63%の高い税率が適用されるため、売却時期によって税負担が倍近く変わる可能性があるのです。
ポイントは、所有期間の起点と判定基準にあります。所有期間は、物件を「取得した日」から「譲渡した年の1月1日までの期間」で判断されます。例えば、2019年12月15日に取得した物件を2024年12月30日に売却すると、所有期間は「5年未満」となり、短期譲渡所得として約39.63%の税率が適用されてしまうため注意が必要です。つまり、このケースのように年末に売却を急いでしまうと、ほんの数日違いで短期譲渡扱いとなり、大きく損をしてしまうケースもあります。売却を予定している場合は、暦年の切り替えを見据えて時期を調整することが有効な節税策となります。
取得費の証拠書類を残す
譲渡所得の計算では「取得費」が重要な役割を果たします。取得費とは、不動産を購入した際の費用や付随費用(仲介手数料、登記費用、取得税など)を指し、売却価格から差し引くことで課税対象となる利益を減らすことができます。これらを正確に計上するためには、購入時の契約書や領収書、登記費用の明細などをしっかりと保管しておく必要があります。
特に注意が必要なのは、リフォーム費用の扱いです。資産価値を向上させるために行った工事(増改築や設備更新など)は取得費に含められる可能性がありますが、単なる修繕や維持管理目的のリフォームは対象外です。線引きが非常にあいまいなため、該当するか不明な場合は税理士などの専門家に事前確認をとっておくと安心です。なお、取得費の証拠がない場合は「概算取得費(売却価格の5%)」とされてしまい、税負担が大きくなる点にも注意しましょう。
経費の計上漏れを防ぐ
不動産を売却する際には、売却のためにかかった諸費用(譲渡費用)も譲渡所得から差し引くことが可能です。代表的なものには、不動産会社への仲介手数料、土地や建物の測量費、建物の解体費用などがあり、これらを「譲渡費用」として計上することで課税対象額を減らせます。
ただし、これらを経費として申告するには領収書や契約書などの証拠資料が必要です。証拠がない場合、税務署に否認される可能性があるため、すべての関連支出を記録・保管しておくことが重要です。経費の漏れがあると、本来なら支払わなくてよかった税金を余計に支払ってしまうことになりかねません。特に複数の費用が発生する大きな売却では、リストを作って1つ1つチェックしておくと安心です。
特例の適用漏れを防ぐ
不動産売却においては「3,000万円特別控除」をはじめとしたさまざまな優遇制度が用意されています。条件を満たせば税金を大幅に軽減できる制度ばかりですが、適用には細かなルールがあり、事前に内容を把握しておかないと、気づかないまま権利を失ってしまうこともあります。
例えば「買換え特例」は売却と購入の期間に制限があり「3,000万円特別控除」は一定期間内に第三者に貸し出していた場合に適用できなくなるケースもあります。必ず売却前のタイミングで税理士や不動産会社に相談し、適用の可否や必要な書類を確認しておきましょう。節税効果を最大限に活かすには、事前準備が何よりも重要です。
譲渡損失が出た場合は譲渡損失の損益通算と繰越控除を活用する
不動産を売却した際、取得費や経費を差し引いても利益が出ず、赤字(譲渡損失)が発生するケースもあります。特に市況が悪い場合や、相続で取得した不動産を安価で売却した場合などは、損失が大きくなることも珍しくありません。このような場合「損益通算」を活用すれば、その損失を給与所得や事業所得など他の所得と相殺し、課税所得を減らすことが可能です。
また、損益通算でも控除しきれなかった損失については、翌年以降3年間にわたり「繰越控除」として適用することもできます。これらの制度は、一定の条件を満たす居住用財産の売却に限定されており、適用のためには確定申告が必須です。税務処理にはやや専門的な知識が求められるため、損失が発生しそうなときは、早めに税理士や不動産会社へ相談することをおすすめします。
不動産売却は税金にも詳しい松屋不動産販売にご相談ください

不動産売却では「いくらで売れるか」だけでなく、「手元にいくら残るのか」まで見据えた戦略が必要です。松屋不動産販売では、譲渡所得税や特例制度に精通したスタッフが在籍し、売却から確定申告まで一貫してサポートしています。売却益が出る場合でも、条件に応じて適用できる控除や特例を事前に精査し「できるだけ税負担を抑え、手取りを最大化する」提案が可能です。
また、相続した不動産の売却や、共有名義の整理など、一般的に複雑になりやすいケースにも対応可能です。松屋不動産販売は、地域に根ざした営業体制を活かし、地元市場の動向を踏まえた最適な売却プランを立案します。「初めての売却で不安」「税金のことがよく分からない」という方も安心してご相談ください。
まとめ:不動産売却は税金で損しないために正しい知識を身につけよう

不動産の売却では、譲渡所得税・印紙税・登録免許税・消費税など、さまざまな税金が関係してきます。これらを理解せずに進めると「予想よりも税金が高かった」「使えるはずの特例を見落としていた」という事態になりかねません。
節税のためには、売却時期の調整や取得費・経費の記録保管、特例制度の活用が重要なカギとなります。そして何より、税金の知識を持った不動産会社や税理士に早めに相談することで、後悔のない売却を実現できます。松屋不動産販売の無料相談を活用し、経験豊富なプロの視点で最適な売却プランを立ててみてはいかがでしょうか。