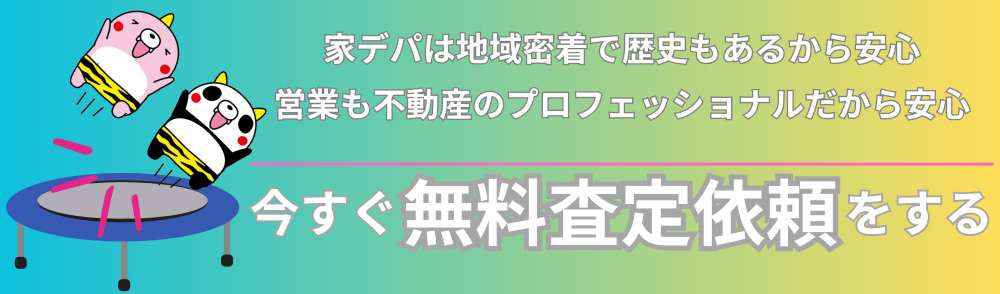相続したマンションが古く「売りに出してもまったく反響がない」状況に直面すると「もう放棄してしまいたい」と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし日本の法律では、個人の意思だけで不動産の所有権を放棄することはできません。一方で、売れないからといって何も対処せず放置してしまうと、管理費や固定資産税などの支払い義務だけが残り、かえって損をするリスクもあります。
本記事では、マンションが売れない場合に放棄できない理由と、売却を成功に導くための現実的な選択肢を解説します。「どうにもならない」とあきらめる前に、できることを見直すきっかけとして、ぜひ参考にしてください。
目次
マンションが売れない場合に「放棄」ができない3つの理由

築年数が古く、買い手がつかないマンションを相続した際「いっそ放棄できればいいのに」と考える方も少なくありません。しかし、現行の法律では、マンションの所有権を個人の意思だけで放棄できず、安易な放置は管理費や固定資産税の負担を長期化させる原因となります。ここでは、マンションを法的に「放棄できない」3つの根拠について整理します。
所有権を放棄することはできない
日本の法律では、不動産の所有権を放棄する制度は設けられていません。たとえ使用しておらず老朽化が進んでいても、登記簿に名前が残っている限り所有者としての責任を負い続けることになります。管理費や修繕積立金、固定資産税といった維持費用は、利用の有無にかかわらず毎年発生し、義務を免れることはできません。
また親族や知人に譲渡したと主張していても、正式に名義変更をしていなければ、法的には引き続き自分が所有者と見なされます。放置が続けば、室内の劣化や郵便物の滞留が発生し、近隣からの苦情や管理組合とのトラブルに発展することもあるでしょう。所有しているマンションが不要と感じても、法的には放棄という選択肢はなく、現実的な解決策を検討する必要があります。
「相続土地国庫帰属法」はマンションが対象外
相続土地国庫帰属法は、不要な土地を一定の条件のもとで国に引き渡すことができる制度です。2023年に施行され、空き家問題への対策として注目を集めましたが、対象となるのはあくまでも「土地」でありマンションは含まれていません。区分所有建物は、専有部分と共用部分が分かれているため、管理が複雑で国が保有するには適さないと判断されています。
たとえ土地と建物をまとめて所有していたとしても、建物部分がマンションであればこの制度の利用は不可です。申請しても却下され、手間や時間を無駄にするおそれがあります。制度の内容を正しく理解し、対象物件かどうかを事前に確認しておくことが大切です。マンションを手放すには、売却や賃貸など、他の現実的な手段を選ぶ必要があります。
相続放棄の期限が過ぎれば放棄できない
不動産を含む相続財産を引き継ぎたくない場合、法的に有効な手段が「相続放棄」です。この制度を利用すると、最初から相続人でなかったものと見なされ、マンションの管理義務や維持費の負担からも解放されます。ただし、申述の期限は厳格に定められており、相続の開始を知った日(通常は被相続人が亡くなったと知った日)から3カ月以内に家庭裁判所へ手続きを行う必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、原則として相続を承認したとみなされ、放棄はできなくなります。また、名義変更を済ませていたり、相続財産の一部を処分・使用していた場合も、放棄の申請は認められません。相続放棄はタイミングと行動次第で権利が消失するため、早めの判断と慎重な手続きが不可欠です。迷った際は、専門家に相談するのが確実です。
マンションが売れない3つの要因

立地や建物の条件、売却価格、仲介業者の集客力など、売れ行きを左右する要因は複数あります。ここでは特に影響が大きいポイントを3つ解説します。なかなか売却が進まないときは、これらの観点から現状を見直すことが重要です。
立地や築年数などによる需要の低下
マンションの需要は、駅からの距離や周辺環境といった立地条件に大きく左右されます。「最寄り駅から遠い」「スーパーや病院が近くにない」「坂道が多い」といった場所では、生活の利便性が低くなり購入希望者の関心が集まりにくくなります。
また築年数が古くなるほど、建物の外観や設備が時代遅れとなり、リフォーム前提で見られてしまう傾向があります。特にエレベーターのない中層階物件や、周囲に新築や築浅物件が多いエリアにおいては、価格を下げても売れにくいケースがあります。買主側は「将来売れるか」という視点でも物件を選ぶため、資産価値の低下が避けられない立地や築年数は大きなマイナス要因になるでしょう。
適正価格より売り出し価格が高い
売却活動が長期化する要因として、最も多いのが価格設定の失敗です。築年数や周辺相場に比べて割高な価格を設定していると、検索段階で候補から外されてしまい、そもそも内覧に至らないケースも多いです。
周辺の成約事例や不動産ポータルサイトなどを参考に、現実的な価格帯を見極めることが必要です。「できるだけ高く売りたい」という気持ちは当然ですが、相場より大きく上回る設定は結果的に売れ残りを招き、価格を下げざるを得なくなるケースもあります。売り出し当初の印象で関心が集まるかどうかが決まるため、価格戦略には慎重な判断が求められます。
不動産会社の集客力が弱い
売却の結果は、不動産会社の集客力によっても大きく左右されます。どれだけ条件の良い物件であっても、購入希望者の目に触れなければ成約にはつながりません。ポータルサイト(SUUMO・アットホームなど)への掲載状況や反響数が少ない不動産会社では、物件の露出が不足し、売却が長引く傾向があります。
また売主の希望ばかりを優先し、販売戦略を練らずに進めてしまう不動産会社にも注意が必要です。ポータルサイトに掲載する写真の質や紹介文などによっても、反響率は大きく変わります。実際には、見せ方ひとつで印象が変わり、購入検討の段階に進むかどうかが決まることもあります。地域や物件特性に応じた戦略を提案できるかどうかも、担当者を見極める重要な判断材料です。
売れないマンションを保有し続ける4つのデメリット

マンションが売れないまま放置されると、時間とともに費用やリスクが増加していきます。ここでは、保有し続けることで生じる4つの主要なデメリットを紹介します。状況を放置せず早めに動くことが、結果的に負担を減らすことにつながります。
維持費が発生する
マンションを所有しているだけで、さまざまな維持費用が発生します。代表的なものが、管理費・修繕積立金・固定資産税といったランニングコストです。たとえ入居者がいなくても、所有者としての支払い義務は発生し、毎月あるいは年単位で請求が届きます。
特に注意が必要なのが、マンションの築年数が進んだタイミングで発生する大規模修繕です。修繕積立金が十分に貯まっていない管理組合では、一時金の負担を求められることもあります。また、固定資産税は毎年課税されるため、長期間売れない物件を保有し続けると、毎年維持費がかかり続けるリスクがあります。
空室で収益が出ない状態であれば、維持費が家計を圧迫する結果になりかねません。費用だけが出ていく状況が続けば、売却や活用の判断が遅れ、損失がさらに膨らむ可能性もあります。だからこそ、マンションを保有し続けるかどうかの判断は、費用面からも冷静に検討する必要があります。
老朽化が進行する
マンションを空室のまま放置していると、室内は見た目以上のスピードで劣化していきます。人が住んでいない空間は換気がされず、湿気や温度変化の影響で建材や設備にダメージが蓄積しやすくなります。キッチンや浴室、トイレなどの水回りは特に劣化が早く、しばらく使っていないことで配管が詰まったり、臭気が上がったりといったトラブルにつながるケースもあるため注意が必要です。
さらに、老朽化が進むと、壁紙のはがれやフローリングの浮き、ドアや窓の歪みといった症状が徐々に現れます。空室だからといって放置していると、いざ売却するときに内見者へ悪い印象を与えてしまうでしょう。
このような状況になると、売却時に値引き交渉の材料にされる可能性もあります。空室は「劣化が進む状態」であることを理解し、定期的なメンテナンスを怠らない姿勢が重要です。
管理の負担・手間がかかる
マンションを保有している限り、入居の有無にかかわらず管理の手間は必ず発生します。例えば室内の換気や掃除、ポストの確認など、空室であっても最低限の管理が必要です。放置しておくと、ホコリの蓄積や湿気による劣化、異臭の発生などが進み、資産価値の低下を招く原因になります。
特に遠方に住んでいる場合、管理のために現地へ足を運ぶ時間や交通費も負担になります。長期で保有していると、年に何度も確認に行かなければならない状況になることもあり、物理的・精神的にもストレスの元にもなりかねません。
さらに区分所有者である以上、管理組合からの連絡や総会・理事会への出席依頼などにも対応が求められます。たとえ売却を予定していても、所有している間は管理組合の一員としての責任を果たさなければいけません。
近隣や管理組合からクレームが入る可能性がある
マンションを空室のまま放置していると、思わぬトラブルの火種になることがあります。室内の換気がされず異臭がこもったり、水回りの湿気でカビや腐敗が進行したりすると、上下階や隣接住戸に悪影響を及ぼすおそれがあります。虫害や水漏れが発生すれば、損害賠償を求められる可能性もあります。
さらに、外部から見える部屋の様子が「空き家のまま放置されている」と受け取られると、防犯や景観の面で近隣からクレームが入ることもあります。
例えば、以下のような状態は、周囲にマイナスの印象を与えたり、空き巣や放火などの犯罪を招いたりする原因になります。
- ベランダに物が積まれている
- 郵便物があふれている
- 玄関まわりに蜘蛛の巣などの汚れが目立つ
- 室内が常に真っ暗で住んでいる気配がない
また、管理費や修繕積立金の支払いが続く中で滞納が発生すれば、状況はさらに深刻になります。一定期間の未納があれば、管理組合からの督促だけでなく、法的措置や差押えに発展する可能性もあります。
マンションが売れない場合に検討すべき3つの選択肢
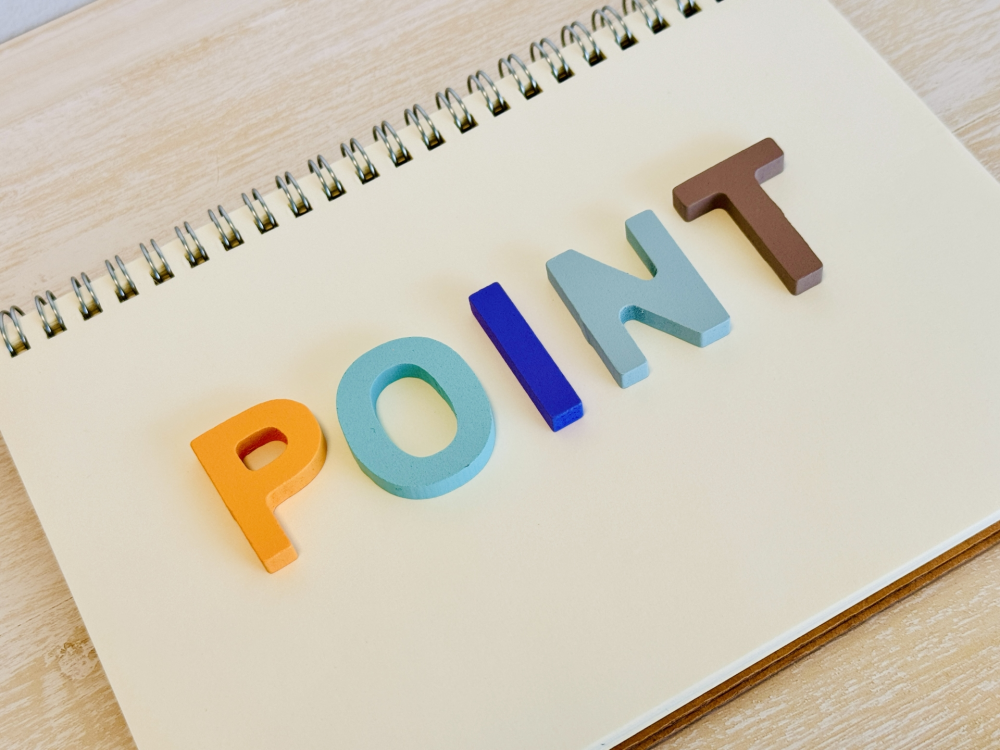
売却がうまくいかないからといって、すぐに「どうにもならない」とあきらめる必要はありません。条件の見直しや業者選びによって、状況が大きく改善することは十分にあります。ここでは、現実的に取り組める3つの選択肢を紹介します。
現在の売却条件を見直す
マンションが売れないと感じたら、まずは売却条件の見直しが有効です。特に売り出し価格が相場よりも高すぎる場合、物件検索の時点で候補から外れてしまい、内覧にもつながりません。周辺の成約事例や相場データをもとに、適正な価格に再設定することで、反響が戻るケースも多く見られます。
特に近年は、買い手が物件を探す際に不動産ポータルサイトの検索機能で「価格の上限」を設定するのが一般的です。そのため、相場より高すぎる価格で売り出している物件は、検索結果にすら表示されず、閲覧される機会すら得られないことがあります。価格が適正であれば、検索結果に表示される頻度も増え、検討候補に入れてもらえる可能性が高まるでしょう。
不動産会社を再考する
売却活動が長期化している場合、不動産会社や担当者の対応に課題がある可能性もあります。「反響が少ない」「内覧が入らない」「販売戦略の提案がない」といった場合は、業者選びの見直しが有効です。他社の査定額や売却方法を比較することで、より適切な販売方針や価格設定が見えてくるでしょう。
また、不動産会社によって得意とする物件種別や販売エリアが異なります。ファミリー向けに強い会社もあれば、投資用ワンルームに特化している会社も存在します。現在依頼している業者が自分の物件と合っていない可能性もあるため、専門性や広告力のある業者へ切り替えることで、売却スピードが一気に改善されるケースも期待できます。
地域密着型の不動産会社に依頼する
全国展開している大手業者も安心感がありますが、地域に根ざした不動産会社には独自の強みがあります。特に地元の相場や購入希望者のニーズを熟知しているため、物件の魅力を適切に伝えることができ、成約につながる確率も高くなります。相談から契約までの対応スピードが早い点も大きな魅力です。
地域密着型の業者は、ポータルサイトだけでなく地元紙や店頭掲示、地域ネットワークによる紹介など、多様な販路を活用します。インターネットだけではリーチできない層にも情報が届きやすくなり、反響の幅が広がります。エリア特性に精通した営業活動により、買い手と物件のマッチング精度が高まり、結果的にスムーズな売却につながるケースが多く見られます。
マンションが売れないとお困りの方は松屋不動産販売にご相談ください

「築年数が古い」「立地に難がある」など、売却が難しいと感じるマンションでも、条件の見直しや販売戦略次第で成約の可能性は大きく変わります。松屋不動産販売では、地域の需要や相場をふまえたうえで、物件ごとに最適な売却プランをご提案します。
大手ポータルサイトへの掲載はもちろん、現地案内の工夫やリフォーム提案、写真の改善など、さまざまな角度から成約につながる対策が可能です。売れにくい物件にこそ、戦略的な販売活動が効果を発揮します。松屋不動産販売では、豊富な経験と知見を持つスタッフが、物件の魅力を最大限に引き出すご提案をいたします。
「なかなか売れない」と感じた段階でご相談いただければ、改善の糸口が見つかるかもしれません。地元密着の対応と柔軟な提案力で、安心して売却活動を進められる体制を整えています。まずは一度、お気軽にご相談ください。
まとめ:マンションが売れない場合は「放棄」ではなく現実的な対策を講じよう

マンションは「いらないから放棄する」ということができない資産です。所有している限り、管理費や税金といったコストが発生し続け、放置すればさらなるトラブルに発展するリスクもあります。相続放棄の期限が過ぎたあとや、売却が思うように進まないときこそ、冷静に対処することが重要です。
まずは売れない理由を正しく見極め、価格や販売方法の見直し、不動産会社の再選定など、実行可能な対策を検討しましょう。放棄できないからこそ早めに専門家へ相談し、状況に合った最善の選択肢を見つけることが、後悔のない売却への第一歩となります。松屋不動産販売では、売却が難しい状況でも寄り添いながらサポートいたします。