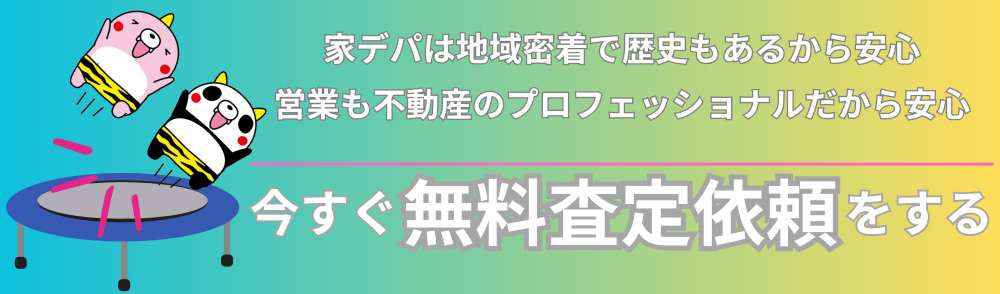田舎の家は、維持費や管理の手間がかかる一方で、なかなか売却が進まず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。地方は都市部と比べて買い手が少ないことから、売却活動が長期化しやすいという特徴があります。
本記事では、田舎の家が売れにくい主な3つの理由と、放置することで生じるリスクを解説します。スムーズな売却方法が理解できる内容になっているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
田舎の家が売れない3つの理由

田舎の家が「売れない」と悩む方は多くいます。その背景は都市部と異なり、住民の減少や高齢化、物件の管理状態や立地条件などが売却のハードルになっているのです。
こうした要素を十分に理解しないまま売却活動を進めてしまうことで、売れるまでに時間がかかったり、価格を下げざるをえなかったりするケースがあります。ここでは、田舎の家が売れにくい理由について解説します。
需要が少ない
郊外エリアでは人口減少や高齢化が進行し、住宅を購入する需要が少なくなっています。特に若年層は、地元に就業先が少ないことから都市部へ流出しており、購入希望者が限られているのが現状です。
また、医療機関や交通インフラなどが都市部ほど整っていない地域では、暮らしにくさを懸念して購入をためらうケースも見られます。買い手側にとっては「利便性が低く生活に不安があるエリア」と映りやすいため、物件の立地がネックになるでしょう。
このような状況下では「買う人がいない」という状態になりやすく、物件の魅力に関係なく売却活動が滞ってしまうことがあります。購入希望者が少ないため、広告や内見に対する反応が鈍く、売却の長期化につながります。
対応できる不動産会社が限られている
郊外の物件は都市部に比べて売却ニーズが低いため、積極的に取り扱う不動産会社が限られます。特に都市部に本社がある大手不動産会社では、営業エリアの対象外となり断られるケースもあるため、事前の確認が必要です。一方で、地元密着型の不動産会社でも、空き家や築年数の古い住宅の売却に十分な経験がない場合があります。
対応に慣れていない不動産会社では、広告や営業を適切に行えず、販売の優先度が下がることもあります。販売活動が後回しになることで、買い手との接点が減り、売れにくくなってしまうでしょう。売却をスムーズに進めるためにも、対象エリアや物件の特性に詳しい不動産会社を選び、早い段階で相談することが大切です。
土地が広く管理に手間と費用がかかる
郊外の住宅は都市部に比べて敷地が広く、その分だけ管理にかかる労力やコストが大きくなる傾向があります。特に雑草の除去や清掃といった日常的な手入れには手間がかかり、所有者にとっては大きな負担となります。
また、広い土地は固定資産税の評価額が高くなりやすく、使用していなくても維持費が増える点も敬遠される要因の1つです。さらに、敷地が広すぎることで「草刈りが面倒」「建物までの距離が遠い」など使い勝手が悪いと感じられ「住まい」としての魅力が伝わりづらくなる場合もあります。
こうした背景を踏まえると、広い土地の活用方法を提示できるかにより、売却の結果が変わります。地域の需要に沿った価格設定や販売戦略を提案できる不動産会社に相談することが、スムーズな売却につながるポイントです。
田舎の家が売れないまま放置する3つのリスク

売却せずに空き家を放置していると、思わぬ出費や地域との関係悪化などにつながる恐れがあります。特に田舎の物件は敷地が広く、日々の管理にかかる手間や費用も大きいため、放置するほど負担が増してしまいます。
状況が悪化する前に適切な対策を講じることが重要です。ここでは、田舎の家が売れないまま放置することで生じる3つのリスクについて解説します。
管理コストがかかり続ける
建物は使っていなくても、所有しているだけで固定資産税や都市計画税といった税金が毎年発生します。特に田舎の物件は敷地が広い傾向があり、草刈りや雨漏り・シロアリ対策などの維持管理には継続的な手間と費用が必要です。
また所有者が遠方に住んでいる場合は、現地までの移動にかかる時間や交通費に加え、清掃や点検などの管理業務を外部に依頼する費用もかかります。こうした出費が続くと、維持を続けるだけでも大きな負担となるでしょう。
さらに、建物を放置すれば劣化が進み、将来的に高額な修繕費や解体費が発生する可能性もあります。今後使う予定がない物件であれば、費用や労力をかけ続ける前に、早期の売却を視野に入れることがおすすめです。
近隣に悪印象を持たれてさらに売れづらくなる
放置された空き家は、雑草が伸びたり窓が割れていたりと、外観の悪化により近隣住民に不快な印象を与える原因になります。さらに、草木の越境や屋根瓦の落下といった問題が発生すれば、通行人や隣人に被害を及ぼす恐れがあり、損害賠償に発展するケースもあるでしょう。
近年、多くの自治体では「生活環境課」などの窓口を設けており、近隣からの苦情に対して所有者へ早急な対応を求めるケースがあります。特に田舎では地域のつながりが密なため、管理が行き届いていない空き家は「迷惑な存在」と見なされやすいです。信頼を失う前に管理体制を見直すか、売却を検討することが大切です。
犯罪や事故のきっかけになる恐れがある
空き家は人の気配がなく、郵便物の溜まり方や草木の伸び方からも放置されていると判断されやすく、犯罪に利用されるリスクを抱えています。特に人目が少ない田舎では、不法侵入や不審者の住みつきといったトラブルが発生しやすく、所有者が対応や清掃・修繕などの費用を負担するケースもあります。
さらにゴミの不法投棄や放火などの被害に発展すれば、物件の印象が悪くなり、買い手から敬遠されて売却の機会を逃す可能性もあるでしょう。こうした問題が地域の安全に影響を及ぼす前に、防犯対策の一環として使う予定のない家は、早めに処分や売却を検討しておくことが重要です。
田舎の家が売れないときの対策5選
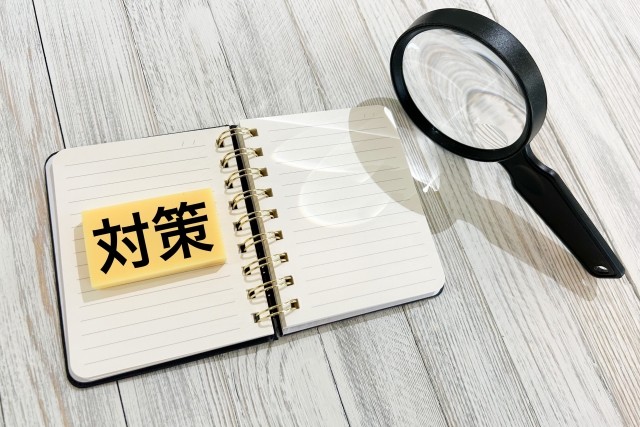
田舎の家は、需要が限られているうえに、建物の状態や立地条件によっては売却につながらないケースも多いです。家が売れないまま放置すると、維持費の増加や物件価値の低下など、さまざまなリスクが発生する恐れがあります。ここでは、田舎の家が売れないときの対処法を解説します。
建物を解体して更地で売り出す
築年数が古く老朽化した建物は、購入後に修繕や解体が必要になるため、買い手に敬遠されやすい傾向があります。特に田舎の物件ではその傾向が強く、建物の存在が購入のハードルになることもあるため注意が必要です。
こうした場合には、建物を解体して更地にすることで買い手が用途を自由に検討しやすくなり、購入希望者の幅が広がります。住宅用地としてだけでなく、駐車場や資材置き場などとしても活用できるため、早期売却につながるケースもあります。
ただし、更地にすると固定資産税の住宅用地特例が外れ、税額が3~6倍になる可能性があるため注意しましょう。費用面や地域性も含め、不動産会社と相談しながら進めることが大切です。
最低限のリフォームや清掃で印象を整える
長期間放置されていた空き家は、外観や室内の汚れ・劣化が目立ち、内見時の第一印象を悪くしてしまいます。こうした印象は購入意欲に直結するため、売却前に最低限の清掃や簡単な修繕を行っておくことが大切です。例えば、水回りのクリーニングや壁紙の張り替えといった手入れは、比較的低コストで印象を改善しやすいポイントです。
すべてをリフォームする必要はありませんが「すぐに住めそう」「大切に管理されてきた家」と感じてもらえる状態にすることで、購入希望者の関心を高められる可能性があります。不動産会社と相談しながら、予算や物件の状態に応じた準備を進めましょう。
相場に合わせて価格を見直す
田舎の物件は需要が限られているため、相場より価格が高いと「割高な物件」と見なされ、購入を敬遠されやすくなります。特に、築年数が古く設備も更新されていない家では、価格が見合っていないと判断されることもあります。
「反響が少ない」「内見が入らない」といった状況が続く場合は、近隣の売却事例や不動産会社のアドバイスを参考に、価格の見直しを検討することが重要です。購入希望者の視点に立ち、適正価格を設定し直すことで検討の対象に入りやすくなり、売却のチャンスが広がります。
また、早い段階で価格を調整すれば、長引くことでかかる管理費や固定資産税の負担を抑える効果も期待できるでしょう。長期的な出費を避けるためにも、一定期間ごとに価格を見直したり、問い合わせの件数に応じて価格を調整するなど柔軟な対応が求められます。
空き家バンクや地域コミュニティを活用する
田舎の物件は、不動産ポータルサイトに掲載しても反響が得にくいことがあります。そのような場合は、市町村が運営する「空き家バンク」や、地域の移住支援団体への登録を検討してみましょう。田舎暮らしを希望する層に情報が届きやすく、マッチングの可能性が広がります。
また、自治体によっては住宅取得の補助金制度が整備されており、買い手にとって魅力的な条件になることもあります。地元の自治会や知人から紹介されて売却が成立するケースもあるため、地域のつながりも積極的に活用すると良いでしょう。公的制度と民間の不動産会社を併用することで、売却の幅を広げることができます。
地域密着型の不動産会社に相談する
都市部を主な営業エリアとする不動産会社では、郊外の需要や相場に関する知識が十分でない場合があり、売却がうまく進まないこともあります。その点、地域密着型で空き家や古家の売却実績がある会社なら「移住希望者や古民家をリフォームして活用したい」といった需要などを把握しています。
また、自治体の補助制度や地域の販売チャネルに詳しいため、古民家再生や定住支援策を活かした販売も可能です。手続きの負担を減らし、スムーズな売却を進めるためにも、地域に密着した不動産会社への相談をおすすめします。
田舎の家が売れずお困りなら松屋不動産販売にご相談ください

田舎の家は、都市部に比べて購入希望者が限られているため、売却が長引いてしまうことも多いです。その間にも、固定資産税や管理費といった維持コストはかかり続けるため「どうすればいいか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
こうしたケースでは、地域特性や市場の動きをしっかり把握している不動産会社に相談することが、売却するために重要となります。特に、空き家や築古物件の売却実績が豊富な不動産会社であれば、適正な価格設定や的確な販売戦略を提案してくれるでしょう。
松屋不動産販売は、静岡県内を中心に数多くの売却サポートを行ってきた実績があります。一人ひとりの状況に寄り添い、丁寧かつスムーズな対応を心がけています。「まずは話を聞いてみたい」「売れるかどうか不安」という方も、どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。
まとめ:田舎の家が売れない場合でも理由を把握すれば対策できる

田舎の家が売れにくい背景には、需要の少なさや建物の老朽化といった要因があります。しかし状況を整理し、適切な対策を講じることで、売却のチャンスは十分に広がります。例えば「築古物件であれば解体して更地にする」「反響が少ない場合は価格を見直す」など、状況に応じて対応を進めていくことが重要です。
「どう進めてよいかわからない」「本当に売れるか不安」といったお悩みがある方は、静岡県で豊富な売却実績を持つ松屋不動産販売にぜひご相談ください。地域密着型の不動産会社として、経験豊富なスタッフが状況に合わせて丁寧にサポートいたします。まずは無料相談から、お気軽にご利用ください。