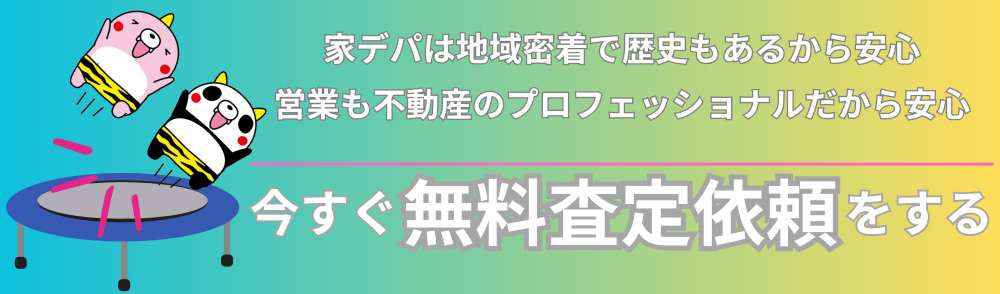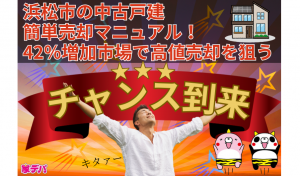使い道のない土地を相続したものの「活用する方法がない」と悩む方も多いのではないでしょうか。土地を活用することなく放置し続ければ、税金や管理の負担がかかるだけでなく、近隣とのトラブルや相続時に意見が対立してしまう可能性もあります。
この記事では、土地を手放す5つの方法を解説します。高く売却するためのコツや土地を放置することによって起こり得るリスクも理解できる内容になっているので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
土地を手放したいときに取れる5つの方法

使い道がなく管理が難しい土地を所有していると、税金や維持管理の負担が重くなります。所有している土地を手放す際は、複数の選択肢があることを理解したうえで自分に合った方法を見つけることが大切です。ここでは、土地を手放したいときに取れる5つの方法を紹介します。
不動産会社に仲介を依頼して売却する
土地を手放すもっとも一般的な方法は、不動産会社に仲介を依頼して売却することです。地域の相場や需要に詳しい不動産会社に相談すれば、査定から販売活動まで対応してもらえます。売却をスムーズに進めるためには、現地の印象が悪化しないよう草刈りを行ったり、ポータルサイト上で土地の活用イメージを伝えたりする工夫も必要です。
場合によっては価格の見直しを検討したり、マッチングサービスを併用して進めたりする判断も求められます。時間に余裕があるうちに相談しておくと、希望時期に売り切るため資金計画を崩したり、焦って値下げしたりするリスクを減らせるでしょう。不動産会社に仲介を依頼することで、スケジュール調整や進行をサポートしてくれるため、納得のいく形で売却活動を進めやすくなります。
隣地所有者への売却や譲渡を打診する
隣地の所有者に声をかけることは、土地を手放すうえで有効な方法の1つです。もし隣接する土地を拡張したいというニーズがあれば、スムーズに売却が進むでしょう。例えば、形がいびつな土地や接道条件が良くない土地でも、隣地と一体で使えば活用価値が高まるケースがあります。
市場の買い手からは敬遠されがちな土地でも、隣地所有者にとっては魅力的な契約になる可能性もあります。隣地への売却交渉は、不動産会社を通じて進めることで、価格交渉や契約条件の調整も安心して行えます。まずは不動産会社に相談し、隣地所有者へのアプローチする際の価格や条件などを検討するのが安心です。
自治体や親族への寄付や譲渡を相談する
土地の買い手が見つからない場合、寄付や譲渡という形で手放す方法もあります。例えば、道路や公園など公共目的で使えそうな土地であれば、自治体に寄付を受け入れてもらえる可能性があります。ただし、すべての土地が対象になるわけではないので注意が必要です。
活用の見込みがなかったり、維持管理にコストがかかったりする土地については、自治体が寄付を断るケースも多くあります。親族へ譲渡する場合でも、相手がその土地を使う意思があるか、固定資産税などの維持負担に問題がないかを事前に確認しておくことが大切です。
特に農地の場合、受け取り側が農業従事者であることや農業設備を保有していることが求められるケースがあります。トラブルを防ぐためにも、手続きを進める前に税理士や司法書士などの専門家や自治体へ相談し、必要な書類や条件をしっかり確認しておきましょう。
国庫帰属制度を活用する
土地を相続したものの使い道がなく、売却も難しい場合には、国に土地を引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」の活用が検討できます。2023年に始まったこの制度は、以下の条件を満たすと、土地を手放すことが可能となります。
- 建物や井戸、工作物などが一切存在しないこと
- 抵当権や通行権など他人の権利が設定されていないこと
- 境界が明確で、争いがなく確定していること
- 土壌汚染や崖地など、特別な管理や改良を要しないこと
加えて、申請手数料や管理費用などの負担も発生するため、費用面と手続きの手間を見越して準備を進めることが必要です。誰でも利用できる制度ではないため、条件を満たさない場合に備えて、他の手放し方と並行して検討しておくと安心です。
土地取引に強い不動産会社やマッチングサービスを利用する
一般の不動産会社では買い手が見つかりにくい土地でも、土地の仕入れや再販に特化した不動産会社やマッチングサービスを活用すれば、手放せる可能性が広がります。例えば狭小地や変形地などの用途が限定される土地であっても、買い手が見つかるケースがあります。
土地のマッチングサービスを使えば、不動産会社を通さず土地を探している個人と直接つながることが可能です。売却価格はやや下がる傾向があるものの、現金化までのスピードや手間の少なさという点では大きなメリットがあります。
ポータルサイトで売れ残ってしまった土地や、反響がまったくないようなケースでも、専門サービスを組み合わせることで選択肢が広がるでしょう。複数の方法を比較し、自身の状況に合ったサービスを選ぶことが大切です。
土地を手放さず放置したときの5つのリスク

土地を使う予定がないため、放置しておいても良いというわけではありません。維持管理が不十分な状態で所有を続けていると、さまざまな問題が発生する恐れがあります。ここでは、土地を手放さずに放置したときの5つのリスクについて解説します。
固定資産税や維持費の負担が続く
土地を所有しているだけで、毎年の固定資産税は必ず発生します。使っていない土地であっても課税対象となるため、収益のない状態でも税金を支払い続けなければならず、家計の負担になる場合もあるでしょう。建物が残っている場合は、倒壊や雨漏りといった老朽化によるトラブルを避けるために、最低限のメンテナンス費用も必要になります。
土地を保有していると維持費が積み重なり、結果的に「使っていないのにコストばかりかかる土地」となってしまうのです。土地を活用したり収益化できる見込みがないのであれば、早めに処分方法を検討することが、金銭面・精神面の両面での負担軽減につながるといえます。
雑草やごみの放置が近隣トラブルにつながる
土地を長期間放置していると、雑草が伸び放題になったり、ゴミが捨てられたりするケースが出てきます。放置したままにしておくと、悪臭や害虫の発生や景観の悪化などが原因となり、近隣住民からの苦情を招きやすくなります。
特に住宅地では、放置された土地が周辺地域の印象を損ねることにもなり、自治会から草刈りや清掃を求められることもあるでしょう。自治体が対応に乗り出し、清掃代行として費用を請求されるケースもあります。このような問題を避けるためには、使っていない土地であっても、定期的に管理を行うか早めの売却や譲渡を検討することが大切です。
治安悪化や犯罪につながる恐れがある
人が住んでいる気配のない土地や空き家は、地域の治安を悪化させる要因になることがあります。不審者の侵入や違法な滞在だけでなく、空き家が違法行為の発生場所として悪用されるケースもあります。草木が生い茂りごみが散乱するような土地は、不法投棄の対象となったり、放火のリスクが高まったりするなど、さまざまな問題の原因となるでしょう。
トラブルのリスクが高まると、周辺住民との関係が悪化し、資産価値の低下にもつながります。土地を活用する予定がない場合でも、定期的に見回りを依頼したり、草刈りを行ったりするなど適切に管理しておくことが、地域との信頼関係や財産価値を守るうえで重要です。
所有者不明土地や特定空き家として扱われる恐れがある
土地や建物を長期間使わずに放置していると、法的・行政的な問題に発展するリスクがあります。例えば、相続登記や名義変更をしないまま放置すると、登記簿上の所有者が不明となり「所有者不明土地」に分類される可能性があります。
所有者不明土地となると、売却や活用の際に手続きが複雑化し、相続人間の合意形成や費用の負担が必要です。また、老朽化した建物を残したままだと「特定空き家」に指定される可能性もあります。
特定空き家に指定されると、自治体から指導や命令を受けたり、固定資産税の優遇措置が外れたりするため、金銭的な負担も増す可能性があるでしょう。将来的な選択肢を狭めないためにも、登記や管理の見直しが求められます。
相続人に負担やトラブルが引き継がれる
土地を使わずに放置していると、将来その管理や負担が相続人に引き継がれることになります。固定資産税の支払いや草刈りなどの維持管理、名義変更などの手続きも相続人が対応しなければならず、想定していなかった手間が発生するケースが多いです。
名義が古いままの土地や境界が不明確な土地では、相続人同士の意見が合わず、トラブルに発展することもあります。実際には利用していなくても、所有しているだけで相続後に費用や責任が発生することに注意しておきましょう。
想定外の費用の支払いを避けるには、生前のうちに土地の売却や相続登記などの名義の整理を進めておくことが大切です。子どもや親族に不要な負担を残さないためにも、早めの対応が望まれます。
土地を少しでも高く手放す3つのコツ

土地をできるだけ高く売却するには、事前の準備が重要です。買い手が購入後の活用をイメージしやすいよう整えておくことで、価格交渉を有利に進められる可能性が高まります。ここでは、土地を少しでも高く手放すための3つのコツを紹介します。
更地にすることで買い手の幅を広げる
古い建物が残っている土地は、解体し更地にしてから売却することで買い手の幅を広げやすくなります。建物がない状態であれば、住宅用地や駐車場、事業用地などさまざまな活用が想定でき、反響も得やすくなるでしょう。
特に老朽化した建物が残っている場合、購入後に解体費用が発生することで、購入のハードルを上げてしまうケースもあります。反対に、更地の状態であれば土地の状態も把握しやすく、見学時の印象も良くなるため、検討が前向きに進みやすくなります。
ただし、更地にすると固定資産税の「住宅用地の特例」が外れる点には注意が必要です。毎年1月1日時点の土地の状態をもとに課税額が決まるため、年内に建物を取り壊してしまうと、翌年度から固定資産税が最大で6倍になるケースもあります。更地にするための費用やタイミングについて不安がある場合は、不動産会社に相談し、売却の見通しや解体費用とのバランスを踏まえて判断するのがおすすめです。
境界や用途地域などの情報を明確にする
土地を購入する人にとって、境界や用途地域などの情報が整理されているかが判断に大きく影響します。境界が不明確なままでは将来的なトラブルを懸念されやすく、成約の妨げになることもあります。
事前に確定測量を行い、接道状況や建ぺい率・容積率などの法的条件を明示しておけば、土地活用のイメージが具体化しやすくなります。整理された情報が載っている土地は信頼性が高く、購入を検討している方からの印象も良くなるでしょう。不動産会社と連携して必要な情報を整理しておくと、価格交渉でも有利に進められます。
需要が高まる時期に合わせて売却を進める
土地を手放すタイミングは自由に設定できないこともありますが、需要が増える時期に合わせて売却活動を進めるのが効果的です。例えば、新年度を前に住宅購入が活発になる1〜3月は、問い合わせが増えやすい時期とされています。3月までに新築戸建に入居を希望する買い手に向けては、その6〜9ヵ月前から動き出すと売れやすくなります。
引っ越しや住み替えの需要が高まるタイミングで売却を始めることで、購入意欲の高い層と出会える可能性が高まり、価格交渉でも優位に進めやすくなるでしょう。住宅購入の資金計画が進む夏や、冬のボーナス時期も需要が高まります。売却時期に応じて訴求するPRコメントや価格の見直しを検討するなど、戦略的に動くことが大切です。
土地を手放したいとお考えの方は松屋不動産販売にご相談ください

土地の活用予定がなく「どう手放せばいいかわからない」とお悩みではありませんか。特に、売却を検討していても「買い手が見つかるか不安」「管理が行き届かず近隣から苦情が出ないか心配」など、不安を抱えたまま放置してしまう方もいらっしゃいます。
松屋不動産販売では、静岡エリアにおける豊富な売却実績をもとに、物件ごとの状況や背景に応じた現実的な売却プランの提案が可能です。他社で断られた土地であっても、過去の取引事例をもとに、柔軟なアプローチで対応いたします。
「売れる見込みがあるか知りたい」「まずは話だけでも聞いてみたい」とお考えの方も、ぜひお気軽に松屋不動産販売にご相談ください。経験豊富なスタッフが、状況に応じた売却をサポートいたします。
まとめ:土地を手放す方法や放置リスクを知って売却を進めよう

土地を手放したいと考えても「何から始めればいいのか分からない」と感じる方もいらっしゃいます。放置すれば固定資産税や管理負担が増し、将来的なトラブルにもつながります。
まずは所有する土地の状況やリスクを把握し、自分に合った手放し方を検討することが大切です。売却のタイミングや準備の工夫次第で、希望に近い条件で売却を進められる可能性が高まります。所有している土地を手放したいと感じたときは、豊富な実績とノウハウを持つ松屋不動産販売にお任せください。