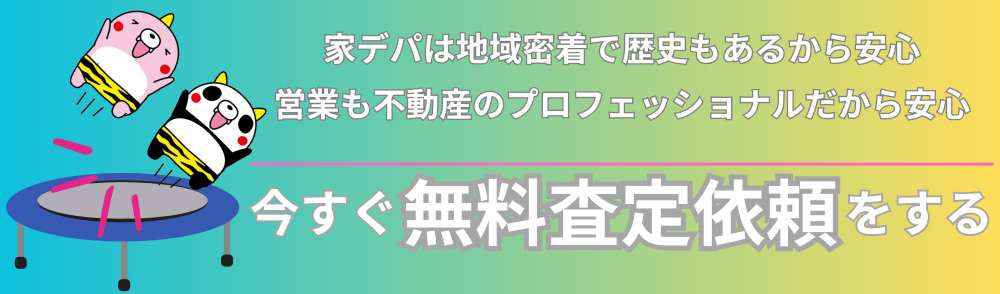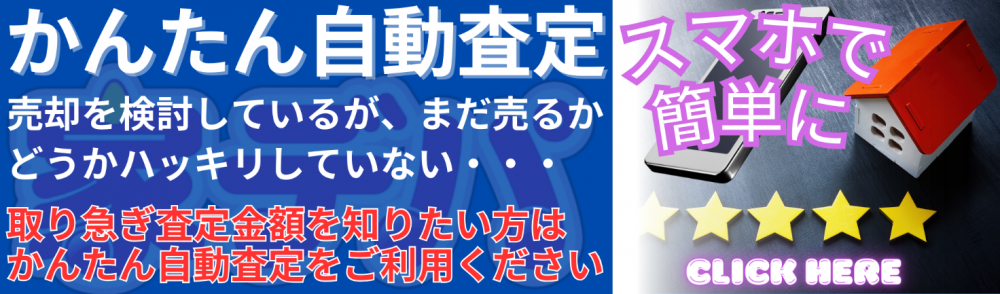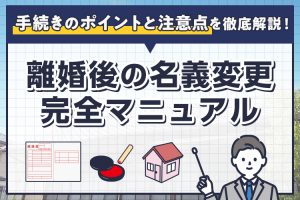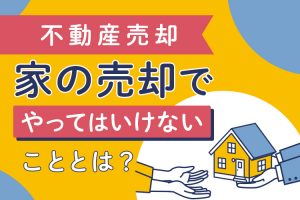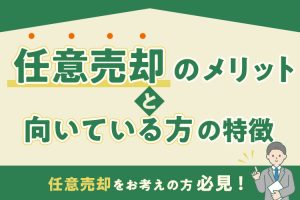親が施設に入居した際、実家をどうするかは多くの家族が悩む問題です。「いつか戻ってくるかもしれない」「思い出の詰まった家を手放すのは心苦しい」という気持ちがある一方で、維持費の負担や管理の手間が重くのしかかります。
また売却を検討しても、親の代わりに売却を進めるのは準備や手続きが複雑で時間がかかることが多いです。そのため売却を検討した際に確認すべきことや、代わりに売却する方法などを事前に把握しておくことが大切です。
そこで本記事では、施設入居後の実家売却を検討する際にまず確認すべきことや家を活用するための4つの選択肢、売却がおすすめの理由、売却タイミングなどについて詳しく解説します。
目次
施設に入った親の家を売却するか検討する際に確認すること

親が施設に入居した際、実家をどうするかは多くの家族が直面する問題です。売却を検討する前には、まず以下の3つを確認するようにしましょう。
- 親の意向
- 将来的な利用の可能性
- 住民票の移動の必要性
これらを事前に確認しておくことが、売却するかどうかを判断する際の参考になります。それぞれ詳しく解説します。
親の意向
親が施設に入ったからといって、すぐに売却の手続きを進めるのは避けましょう。何よりもまずは、親自身の気持ちを最優先に考えることが大切です。長年暮らしてきた家には、たくさんの思い出があり、簡単に気持ちを整理できない方も多いでしょう。「いつか家に帰りたい」「思い出の詰まった家を手放したくない」という想いを抱いている場合、家族が経済的な理由だけで売却を急ぐと、親子関係に深刻な亀裂が生じる可能性があります。
親の認知機能に問題がない場合は、施設での生活に慣れた頃を見計らって、家族で話し合いの場を設けることが重要です。話し合いでは親の意向を十分に尊重しつつ、現実的な維持費用や管理の負担についても率直に相談しましょう。感情的な部分と現実的な課題の両方を家族全員で共有し、全員が納得できる結論を導くことが、実家売却を成功させる重要なポイントとなります。
将来的な利用の可能性
実家の売却を検討する際には、将来的に利用する予定がないのかも考慮しましょう。現在は別の場所に住んでいても、定年後に実家に戻る予定があったり転職や転勤で住む場所が変わる可能性があったりする場合は、売却を急ぐ必要はありません。また、家族のなかで将来的に実家に住む可能性がある人がいるかどうかも、改めて確認しておくことが重要です。
特に実家の立地条件が良い場合や、大規模なリフォームをすれば十分住める状態の場合は、売却以外の選択肢も考えられます。駅近や商業施設へのアクセスが良い立地であれば、将来的な資産価値の向上も期待できるでしょう。
一方で家族の誰も住む予定がなく、年間の維持費が家計を圧迫する状況であれば、早めに売却を検討することが現実的な選択肢となります。感情的な愛着だけでなく、長期的な経済的負担も含めて総合的に判断することが重要です。
住民票の移動の必要性
施設入居に伴う住民票の取り扱いは、介護保険制度との関係で重要なポイントとなります。
法律上、住居があるところに住民票があるのが原則になります。そのため、親が施設に入居した場合、施設所在地が新たな住居となり、住民票もそちらに移すのが一般的です。
ただし、親が施設で利用する介護保険は、原則として住民票のある市町村が保険者となります。つまり、介護保険料を住民票がある自治体に納付し、その市町村から介護給付を受けることになります。
しかし、施設がある自治体と親の実家がある自治体が異なる場合には「住所地特例」という制度の利用が必要です。この特例により、介護施設に入居する前に住んでいた住所の市町村の介護保険を継続して利用できます。施設入居のためにほかの自治体に住民票を移しても、元の自治体の介護保険制度を引き続き利用でき、保険料の急激な変動を避けられます。
施設に入った親の家を活用する選択肢

親が施設に入居したあとの実家について、売却以外にも活用する方法はいくつかあります。それぞれの選択肢にメリットとデメリットがあるため、家族の状況や実家の立地条件、築年数などを総合的に考慮して検討することが重要です。以下の表で、主な活用方法を比較してみましょう。
|
選択肢 |
メリット |
デメリット |
|
売却 |
・まとまった資金を介護費用に充当できる ・維持管理費の負担がなくなる ・3,000万円控除を利用して大幅に減税できる |
・思い出の家を手放すことになる ・売却に時間と費用がかかる ・一度売ると元に戻せない |
|
賃貸に出す |
・月額家賃収入を介護費用に充当できる ・資産として家を残せる ・将来的に家族が住める |
・大幅なリフォーム費用が必要な場合がある ・空室リスクや管理の手間がかかる ・3,000万円控除が使えなくなる |
|
空き家のまま放置する |
・売却の判断を先送りできる ・将来の地価上昇に期待できる ・思い出の家をそのまま保持できる |
・維持費が継続的にかかる ・特定空き家に指定されるリスクがある ・建物の劣化が進行しやすくなる |
|
自ら住む |
・親との思い出を大切にできる ・家の管理が行き届く |
・現在の住まいと実家のそれぞれの維持費がかかる ・現在の住まいを手放す場合には引越し費用がかかる ・立地によっては通勤や生活が不便になる |
どの選択肢にも一長一短があるため、経済的な負担と感情的な価値のバランスを考慮することが大切です。家族の将来設計や親の介護費用の見込み、実家の立地条件や建物の状態などを総合的に考慮し、最適な選択をしましょう。
施設に入った親の家は売却するのがおすすめな5つの理由

施設に入った親の家を活用する方法には、賃貸に出したり空き家のまま放置したりも検討できますが、特におすすめなのは売却です。売却がおすすめの理由は、以下の5つです。
- 売却益を介護費用に充てられる
- 家の維持管理費の負担から解放される
- 空き家として放置した場合のリスクを回避できる
- 相続トラブルを未然に防げる
- 税制優遇を活用できる
それぞれ詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
売却益を介護費用に充てられる
施設に入った親が直面する課題の1つが、継続的な介護費用の確保です。介護付き有料老人ホームの場合、以下のような費用で年間数百万円の費用が発生することもあります。
- 入居一時金
- 月額利用料
- 医療費
- 生活用品代 など
親の年金だけでは賄いきれないことが多く、その結果、子世代が毎月数万円から十数万円の経済的負担を負うことも珍しくありません。親の介護が長期化した場合、子世代の家計にも深刻な影響を与える可能性があります。しかし、実家を売却すれば、まとまった資金を一度に確保できます。
家の維持管理費の負担から解放される
空き家となった親の家は、誰も住んでいなくても、さまざまな費用がかかり続けます。まず確実に発生するのが、固定資産税・都市計画税です。課税額は不動産の規模によって異なりますが、数十万円もの税金が課されることも多いです。さらに以下のような費用が年間を通じてかかるため、継続的な出費が必要です。
- 火災保険料
- 定期的な清掃や草刈り
- 給排水設備の点検
- 電気設備の維持 など
築年数が古い家の場合は、屋根の雨漏り修理や外壁の補修、給湯器の交換など突発的に数十万円から数百万円の修繕費用が発生する可能性があります。これらの費用は予測が難しく、家計への負担も大きくなりがちです。
売却すれば、これらの維持費用が一切不要になります。年間30万円の維持費が浮けば、その分を親の介護費用に回すことができ、家族の経済的負担を大幅に軽減できるでしょう。
空き家として放置した場合のリスクを回避できる
空き家を適切に管理せずに放置し続けると、法的・経済的なリスクに直面する可能性があります。なかでも注意が必要なのが、建物全体の著しい老朽化や部材の破損、衛生上有害な状態などが原因で市町村から「管理不全空き家」や「特定空き家」に認定されることです。
「特定空き家」に認定されると、固定資産税の住宅用地特例が外され、税額が最大6倍に跳ね上がるため、経済的な負担が増大します。さらに、自治体からの修繕命令に従わない場合は50万円以下の過料が科せられ、最悪の場合、行政代執行により強制的に解体されて解体費用を自ら支払うことになります。
また、老朽化した建物の倒壊や漏電による火災の発生により近隣住民が被害を被ると、所有者が損害賠償責任を負う可能性が高いです。売却すれば、これらのリスクを回避でき、安心して生活を送れるでしょう。管理不全空き家や特定空き家については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
相続トラブルを未然に防げる
不動産の相続は、家族間のトラブルが発生する原因になりやすいです。現金と異なり、不動産は物理的に分割できません。そのため「誰が相続するか」「どのように活用するか」「維持費用は誰が負担するか」などの問題で、相続人同士が対立するケースがあります。
特に相続人が複数いる場合、それぞれの経済状況や価値観の違いから、話し合いが長期化することも珍しくありません。実家に愛着がある人と売却したい人の間で意見が対立し、家族関係が悪化することもあります。
一方、親が存命中に売却して現金化しておけば相続時に公平に分割でき、トラブルを未然に防ぐことが可能です。また親が生前に自宅を売却する場合、居住用財産の3,000万円特別控除の特例を活用できる可能性があります。
これにより売却益が出た場合でも税負担を大幅に軽減できるため、相続後に売却するよりも経済的メリットが大きくなります。実家を相続した際の注意点や活用方法に関しては、以下の記事でも詳しく解説しているので併せてご覧ください。
関連記事:実家を相続した方必見!売却の際の注意点や他の活用法を紹介!
税制優遇を活用できる
売却時期によって、税負担を大幅に軽減または完全に免除できる優遇制度を活用できます。主な優遇制度には、以下の3つがあります。
|
優遇制度 |
内容 |
|
居住用財産の3,000万円特別控除 |
親(所有者)が生前に自宅を売却する場合に適用される特例で、売却益から最大3,000万円を控除できる |
|
相続空き家の3,000万円特別控除 |
相続により取得した空き家を売却する場合に適用される特例で、一定の要件を満たせば最大3,000万円の控除が受けられる |
|
小規模宅地等の特例 |
被相続人が自宅として使用していた土地を、配偶者または同居していた親族が相続する場合に適用される特例で、土地の相続税評価額を最大80%減額できる |
これらの特例を効果的に活用することで、売却に伴う税負担を最小限に抑えることが可能ですが、それぞれに適用要件や期限があるため、税務署や税理士などの専門家と相談しながら進めるのがおすすめです。
参照元:国税庁|No.3302 マイホームを売ったときの特例
参照元:国税庁|No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
参照元:国税庁|No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
施設に入った親の家を売却する3つの方法
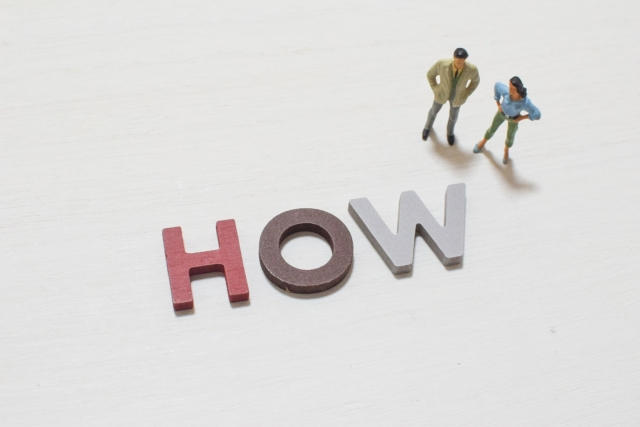
不動産売買では、原則として、物件の所有者(登記名義人)本人が立ち会い、契約する必要があります。しかし親が施設に入居した場合は、移動が困難だったり、手続きが複雑だったりと体力的な負担が大きいため、本人が直接売却手続きを行うのが難しいことも多いです。
また、認知症が進行して判断能力が低下した場合は、法的に売買契約を結べなくなります。そこで、親の状況に応じて適切な売却方法を選択する必要があります。ここでは、3つの主要な売却方法について詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
【意思能力がある場合】任意代理人を立てる
親に売却の意思があり、認知症などで意思能力に欠ける状態ではない場合には「任意代理人」を立てて売却を進められます。任意代理人は特別な資格が必要なく、誰でもなれるため、子が親の代わりに売却手続きを進めることも可能です。
ただし代理人として活動するには、親からの「委任状」が必要となります。委任状には売却価格の下限や売却相手の条件、権限の範囲などを明確に記載し、親子間で認識にずれが生じないよう、事前にしっかりと話し合うことが大切です。
注意点として、売買登記の際は任意代理人がいても、司法書士による親本人への意思確認と署名押印が法的に欠かせません。そのため、親の体調や認知機能に問題がないうちに手続きを進めることが重要です。
【意思能力に欠ける場合】成年後見制度を利用する
親が認知症などで意思能力を欠く状態と判断された場合は「成年後見制度」を利用する必要があります。まず家庭裁判所に申立てを行い、審判により「成年後見人」が選任されれば、後見人が親に代わって売買契約を結べます。ただし、居住用不動産の売却については裁判所の許可が必要となるため、売却理由を明確にしたうえでの許可申請が必要です。
また本制度は、一度開始すると途中で解除できず、不動産取引だけに限定して利用できません。必ずしも親族が後見人に選ばれるとは限らず、家庭裁判所が第三者の専門家を選任することもあります。
弁護士や司法書士が後見人に選任された場合は、月額2〜6万円程度の報酬が継続的に発生します。さらに申立てから審判まで1〜3ヶ月程度の期間がかかるため、売却を急いでいる場合は早めの手続きが必要です。成年後見制度に関しては、以下の記事でも詳しく解説しているので併せてご覧ください。
関連記事:不動産売却×成年後見制度|初めての方でも十分わかるシンプル解説
【入居前の予防策】家族信託を事前に設定する
親が施設に入居する前には、将来の認知症に備えて、親が元気なうちに「家族信託」を設定しておく方法も効果的です。これは親(委託者)が子(受託者)に「不動産を売却する権限」を信託することで、親が認知症になった場合でも、子が売却手続きをスムーズに進められる仕組みです。
成年後見制度のような複雑な手続きや裁判所の許可は不要で、柔軟な財産管理が可能となります。ただし、将来的に売却を想定している場合は、信託契約書に「換価処分」(管理財産を売却してお金に換えること)の権限を明記し、信託登記にもその旨を記載しておく必要があります。
家族信託は将来的な備えとして有効な手段ですが、法的・税務的な専門知識が必要です。不動産の信託登記も必須となるため、司法書士などの専門家への相談が不可欠です。施設入居を検討している段階で、早めに不動産会社の担当者や司法書士、税理士などと相談することをおすすめします。
施設に入った親の家を売却するタイミング

実家の売却を決断した場合には「いつ売却するか」のタイミングが重要です。なぜなら売却時期によって活用できる税制優遇が異なり、手続きの複雑さや家族への負担も変わるためです。ここでは、以下2つのタイミングについて、それぞれのメリットと注意点を解説します。
|
売却するタイミング |
所得税の有無 |
相続税の有無 |
利用できる特例 |
|
親が施設に入居したとき |
有 |
無 |
居住用財産の3,000万円特別控除 |
|
相続が発生したあと |
有 |
有 |
・相続空き家の3,000万円特別控除 ・小規模宅地等の特例 |
親が施設に入居したとき
可能であれば、親が施設に入居したタイミングでの売却がおすすめです。この時期であれば、親の判断能力もまだしっかりしているため、委任状による代理売却もスムーズに進められる可能性が高いです。また、複雑な成年後見制度を利用する必要がないため、手続きが簡単で費用も抑えられるメリットがあります。
「居住用財産の3,000万円特別控除」を活用できる点もメリットといえるでしょう。注意点として、親が住まなくなった日から3年目の12月31日までという期限があるため、早めの決断が必要です。
また、売却で得た資金をすぐに介護費用に充当できるため、家族の経済的負担を大幅に軽減できる点も大きなメリットです。施設の月額費用や一時金の支払いに充てることで、長期的な資金計画を立てやすくなります。
ただし、施設入居から1年程度は、親が新しい環境にまだ慣れていない可能性もあります。そのため生活が落ち着いた頃を見計らって、家族で売却について話し合いを始めることが大切です。「もう家には戻らない」と納得してから売却すれば、親に後悔させてしまう可能性を減らせるでしょう。
相続が発生したあと
一人暮らしをしていた親が亡くなり、相続が発生した場合には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」が適用でき、最大3,000万円の控除を受けることが可能です。この特例は、配偶者がすでに他界しており、親が独り身だった場合に限定されます。また、売却する家屋が現行の耐震基準を満たしている必要があるため、築年数が古い場合は耐震診断や改修工事が必要になる可能性もあります。
相続後の売却では、遺産分割協議がまとまってからの売却となるため、相続人全員の合意があることが前提です。また相続税の申告期限は、相続の事実を知ってから10ヶ月と決められています。売買には一定の時間がかかるため、できるだけ早めに売却活動を始めることをおすすめします。さらに、相続時には「小規模宅地等の特例」による相続税軽減も活用できる可能性があるため、不動産会社の担当者や税理士と相談しながら最適な方法を検討しましょう。
静岡県で家の査定を依頼するなら松屋不動産販売にお任せください

施設に入った親の家の売却を検討中の方は、ぜひ松屋不動産販売株式会社にご相談ください。松屋不動産販売株式会社では、浜松市・湖西市・磐田市をはじめとする静岡県下すべての地域で、経験豊富なスタッフが対応しています。
これまでに2,000件以上の売却実績があり、さまざまなケースの不動産売却に対応してきた豊富なノウハウがあります。さらに松屋地所グループの複数チャネルを活用することにより、売主様と購入希望者が最適な形でマッチングすることが可能です。
税制優遇の活用方法や売却タイミング、法的手続きなどの悩みや課題に対して、お客様一人ひとりの状況に合わせた売却戦略をご提案いたします。売却を検討している方は、まずは以下のリンクから無料査定をお試しください。
まとめ:施設に入った親の家の売却を検討する際には早めに不動産会社に相談しよう

施設に入った親の家の売却は、介護費用の確保や維持費負担の軽減、空き家リスクの回避などのメリットがあります。ただし、不動産売買は基本的に所有者本人が進める必要があり、親の代わりに売却する場合には、準備や手続きが複雑になります。複雑な手続きや税制については専門知識が必要なため、早めに信頼できる不動産会社に相談しましょう。