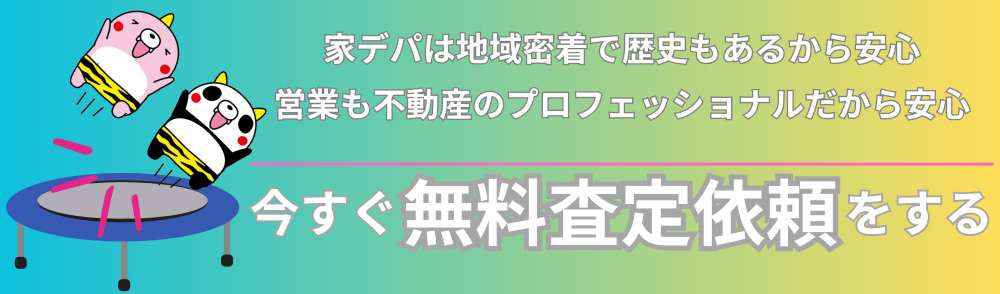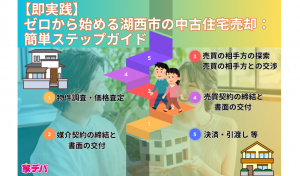「土地を手放したいが、なかなか売れない」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。売れない土地には、面積や地形などいくつか共通する特徴があります。しかし、適切な対処をすれば売れる可能性があるため、売主として行うべき手段を知っておくとよいでしょう。
この記事では、売れない土地の特徴や効果的なアプローチ方法などを解説します。「土地を売り出したが、全然買主が現れない」「相続で活用予定がない土地を取得して困っている」など、土地が売れない悩みを解消できる内容になっているため、ぜひ最後までご覧ください。
目次
【対策あり】売れない土地の代表的な特徴9選

土地を売り出しても、購入希望者のニーズと合わなければ、なかなか買主は見つかりません。ここでは、売れない土地の特徴を解説します。
狭すぎるまたは広すぎる
土地の面積が極端に狭い場合、建築基準法の制約により、希望する建物を建てられない可能性があります。そのため建ぺい率や容積率の制限があると、なかなか買主が見つかりません。一方で、個人の住宅用途としては広すぎる土地も、使い勝手が悪く敬遠されがちです。
広い土地は維持管理費用や固定資産税の負担が重くなる点も、買主がなかなか現れない理由です。買主が不動産会社や建築会社に絞られるため、スムーズに売れない可能性があります。広大な土地は分割して販売することも可能ですが、造成費用や分筆手続きなどのコストが発生するため、買主が不動産会社や建築会社に限定されやすくなります。
狭すぎたり広すぎたりする土地は、地域の事情に詳しい不動産会社に相談して、買主候補となる層を調査してもらうとよいでしょう。
地形がいびつ
不整形地や極端な傾斜地、細長い土地などは建築の制約が大きく、買主が現れにくい傾向にあります。購入しても、希望通りの建物を建てられない可能性があるためです。
急傾斜地では、造成工事に多額の費用がかかるほか、擁壁工事が必要になる場合もあります。土地を活用するためのコスト負担が重くなりやすいため、整形地と比較すると魅力が低い点は否めません。
売り出しても買主が現れない場合は、隣接する土地の所有者に買い取りを打診したり、相場よりも価格を下げたりする方法が考えられます。
土壌汚染や地中障害物などの問題がある
有害物質による土壌汚染の可能性があったり、地中に古い基礎や廃材などの障害物が埋まったりしている土地は、一般的に敬遠されます。
除去費用が発生したり、地盤の軟弱性が問題視されたりする点が、購入を躊躇する要因となるためです。また、地盤改良工事が必要になると追加費用が発生する可能性がある点も、買主が見つかりにくい理由の1つです。
汚染や障害物などの問題を抱えている土地は、あらかじめ売主自身がお金を負担して、専門の会社に浄化を依頼することをおすすめします。土地の調査には専門的な知識と技術が必要になるため、不動産会社に相談するとよいでしょう。
関連記事「古家付き土地を売却する際の6つの注意点!回避策と手放し方も解説」
境界が不明確
隣地との境界線が曖昧な土地は、お互いが「ここまでが自分の土地」と主張し合う境界紛争のトラブルに発展するリスクがあります。実際にトラブルに発展すると心身ともに疲弊するため、購入を避ける方は多いです。土地が売れる可能性を高めるためにも、測量を実施して境界を確定させておきましょう。
境界杭が設置されていない場合は、測量による境界確定作業が必要です。境界の確定作業は土地家屋調査士に依頼する必要があり、30万〜50万円程度(土地の規模や複雑さにより変動)の費用が発生します。
権利関係が複雑
共有名義や借地権、地上権など複雑な権利関係がある土地は、購入手続きが煩雑になりがちです。複数の共有者がいる場合は、処分する際に全員の同意が必要となるため、なかなか買主が見つからないのが実情です。
そのため、共有名義の場合は他の共有者から持分を買い取るか、持分を他の共有者に売却して単独名義にする方法があります。借地権や地上権が設定されている場合は、権利者との協議により権利を解消するか、買い取りを検討するとよいでしょう。
抵当権や根抵当権が残っている場合は残債務を確認し、金融機関と協議のうえ必要に応じて抹消手続きを行います。権利関係をできるだけシンプルにすれば、買主の不安を軽減でき、売却しやすくなるでしょう。
自然災害リスクが大きい
洪水や土砂災害、地震などの自然災害リスクが高い地域の土地は、安全面の懸念があります。特にハザードマップで危険区域に指定されている土地は、災害時の被害を恐れて購入を見送られることがあります。
河川の氾濫原や急傾斜地崩壊危険区域、液状化の可能性が高い地域などは、建築制限がかかる場合もあるため注意が必要です。過去に自然災害が起こった地域は、心理的にも敬遠されやすく、売却のハードルは高くなります。
対策としては、自然災害リスクを織り込んだ価格設定にしたり、住宅用地以外の用途(資材置き場や太陽光発電設備など)での活用を提案したりする方法が考えられるでしょう。
居住環境が悪く需要が低い
居住環境が悪い地域の土地は、需要が低く買主が現れにくい傾向があります。具体的には、交通アクセスが悪かったり、近隣に店舗や病院がなかったりする土地が該当します。
電車やバスの本数が少ないと、通勤・通学に不便です。商業施設や医療機関、学校などの生活利便施設が遠い場合、特に高齢者や子育て世代からは興味を示されない可能性があります。
需要が低い土地を売る場合は、不動産会社と相談しながら、ターゲットを絞る必要があります。ターゲットに対して効果的な訴求となる販売戦略を考え、価格の変更も検討しましょう。
心理的瑕疵がある
過去に事件や事故、自殺などが発生した土地は、心理的な抵抗を持たれます。時間の経過とともに心理的な影響は薄れるものの、完全に解消されることは少なく、長期間にわたって影響を与えることがあります。
工場や墓地、火葬場などの嫌悪施設が近くにある土地も同様です。騒音や臭気、景観の問題から敬遠されやすく、売却が難しいケースが少なくありません。
なお、心理的瑕疵がある不動産には告知義務があります。法律を遵守しつつ、住宅用地以外の用途での活用も視野に入れ、心理的な抵抗感を薄める対策が必要です。
販売価格が相場よりも高い
周辺の取引事例と比較して明らかに高い価格設定の土地は、なかなか売れません。売主の希望価格と市場価格に大きな乖離がある場合、長期間にわたって売れ残ってしまうでしょう。「長期間売れ残っている土地」という印象を持たれ、さらに買主が見つかりにくくなる悪循環になりかねません。
不動産は「一物多価」とも呼ばれるため、市場の状況や買主の資産状況によって、販売価格は左右されます。周辺の競合物件を確認して「〇万~〇万円の間が相場だろう」というイメージを持ちつつ、適正な価格を設定しましょう。
土地が売れないことで発生する特徴的な4つの問題

土地が売れない期間が長引くと、経済的・精神的な負担が重くなります。ここでは特徴的な問題を4つ紹介するので、具体的にどのような負担が発生するのかを把握し、対策を考えましょう。
管理コストが発生し続ける
売れない土地を所有し続けることで、固定資産税や都市計画税などのコストが毎年発生し続けます。買主を見つけるためには適切な管理も重要で、雑草の除草作業や不法投棄の防止対策などの手間や、土地の維持管理費用も負担しなければなりません。
適切な管理を怠ると、近隣住民とのトラブルの原因になったり、行政指導や罰則の対象となる可能性があります。経済的・心理的な負担が発生する点は、活用予定がない土地を持ち続けるデメリットです。
価格が下がり続ける
土地が長期間売れずに市場に残り続けると「売れ残り物件」というイメージが定着し、価格下落の圧力を受けます。相場を後追いして値下げをするケースも多く、売れない期間が長引くほど、価格が下がり続ける悪循環になりかねません。
精神的な負担になる
売れない土地を抱えると、毎月の管理費用や税金の支払いに対する経済的プレッシャーや「いつ売れるのか」という不安が継続的にのしかかります。
特に、相続で取得したものの使う予定がない土地は、できるだけ早く手放してスッキリしたいと考えるのが一般的な感情です。「早く売りたいけど、売れない」という状況は、多少なりともストレスとなるため、精神的に疲弊してしまうでしょう。
相続が発生すると権利関係が複雑になる
土地が売れない中で自身の相続が発生すると、権利関係が一層複雑になります。相続人が複数人いると、意思疎通や合意形成がより困難になり、子ども世代に迷惑をかけてしまうかもしれません。
一般的に、共有者が増えると売却方針について意見が分かれ、土地の処分がさらに難しくなります。土地が売れない状況に拍車がかかってしまい、結局放置され続ける事態になりかねません。
売れない土地が抱える課題を解決する5つのアプローチ

土地が抱える問題や課題を把握したら、買主が安心して購入できるように、対策を施す必要があります。ここでは、売れない土地が抱える課題を解決するアプローチを紹介します。土地の状況や周辺環境に合わせて、適した対策を施しましょう。
販売価格を見直す
売主として「できるだけ高く売りたい」と考えるのは、自然な感情です。しかし、市場価格と乖離した高い価格設定は売却を阻害する要因となるため、見直しが必要です。
周辺の土地相場を調査したうえで、自分の土地の形状や面積などを加味して、適正な価格を算定しましょう。地域での販売実績が豊富な不動産会社のアドバイスを受ければ、適正な価格設定が可能です。
関連記事「不動産売却が進まない原因と改善案を解説!誰でも5分で実践可能」
仲介を依頼する不動産会社を見直す
土地が売れない理由が、実は「不動産会社の営業不足」というケースもあり得ます。土地の形状や権利関係などに問題がない場合、不動産会社の営業力や販売戦略に問題がある可能性が否定できません。
売り出してもなかなか成果が出ない場合は、仲介を依頼している不動産会社の見直しを検討しましょう。現在の担当者が土地の特性を理解できておらず、積極的な営業活動を行っていない場合は、信頼できる不動産会社に仲介先を変更することで状況が改善する可能性があります。
土地の調査を行う
軟弱な地盤や土壌汚染など、土地が何らかの問題を抱えている場合、それらの問題を解消する必要があります。安心して住めない状況だと買主を見つけるのは難しいため、専門的な調査を行ったうえで、対策を打ちましょう。
土地が抱えている問題を解消すれば、買主の不安や疑問を払拭でき、売却しやすくなります。
隣地の所有者に売却を打診する
隣地所有者に対して、売却を打診する方法があります。隣地所有者にとって、形状が整ったり、容積率を最大限活用できたりするメリットがあるためです。
当事者同士では、スムーズに交渉が進まない可能性があります。そのため、不動産会社を交えて、土地を購入するメリットを隣地所有者に対して魅力的に訴求しましょう。
「相続土地国庫帰属制度」を活用する
相続や遺贈で取得した土地に関しては、2023年4月に開始された相続土地国庫帰属制度を利用すると、国に引き渡せます。なお、以下の土地は引き取ってもらえないため、注意が必要です。
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
要件を満たしていることに加えて、申請が承認されたら10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。利用にあたってハードルはあるものの、利用する予定がなく、有効活用できる可能性も低い土地は、相続土地国庫帰属制度を通じて手放すことも検討しましょう。
なかなか売れない土地にお悩みの方は松屋不動産販売にご相談ください

土地の売却には、境界の確認や相場の把握、税金の知識など専門的な対応が求められます。希望に近い条件で土地を売却するためには、信頼できる不動産会社に相談することが大切です。
なかなか売れない土地は、何らかの問題を抱えていることが多いと考えられます。販売実績が豊富で、信頼できる地元の不動産会社に相談すれば、解決方法を見出せるかもしれません。
松屋不動産販売株式会社では、地域に根差した豊富な取引実績と相場感をもとに、適正な価格査定と丁寧な売却プランを提案しています。静岡県内で信頼できる不動産会社を探している方は、松屋不動産販売にご相談ください。
まとめ:売れない土地でも特徴を知ることで問題を解決できる
売れない土地でも、課題を正しく理解すれば解決の糸口は見つかります。面積や地形の問題、土壌汚染などの課題は、適切な調査と対策により克服することが可能です。
また、市場相場に見合った価格を設定し、信頼できる不動産会社に相談することも大切です。専門知識を持つ不動産会社に相談し、最適な売却戦略を実践することで、売れない土地を保有し続けるストレスから解放されましょう。